ブログ詳細
人件費を固定費から変動費に変える方法とメリットは?人件費の削減ポイントも解説
公開日 : 2025.07.22
更新日 : 2025.07.22
企業経営で常に課題となるのが「人件費」です。固定費として膨らむ人件費を変動費化することで、景気変動に強い柔軟な経営が可能になると言われますが、果たして本当にメリットばかりなのでしょうか。
本記事では固定費と変動費の違いから、人件費を変動費化する方法や、そのデメリット、削減のポイントまでをわかりやすく解説します。
コスト体質を見直したい経営者の方は必見です。明日から実践できるヒントもお届けしますので、ぜひ最後までご覧ください。
人件費を固定費ではなく変動費にするメリット
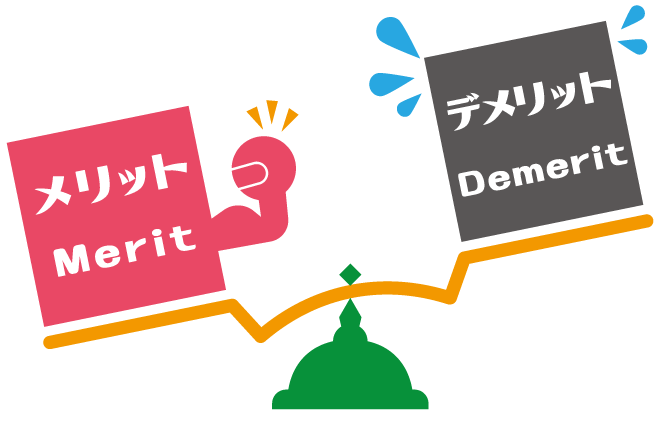
人件費を固定費から変動費にシフトさせることで、経営はより柔軟に、そしてリスクに強くなります。売上に応じて人件費を調整できるため、景気悪化や業績不振の際のダメージを軽減しやすくなるのが大きな魅力です。
ここでは、人件費を変動費化することで得られる具体的なメリットについて、分かりやすく整理してご紹介します。
固定費の削減
人件費を一部変動費化することで、景気や市場が悪化した際に固定費の負担を軽減できます。
売上に応じて人件費を調整できるため、利益の多くが人件費に充てられる傾向(労働分配率)を適正に保ちやすくなります。
2019年度の労働分配率は大企業で54.9%、中小企業で77.1%と高く、過剰なら経営を圧迫し、低すぎれば従業員の士気を下げます。変動費化は売上減少時の分配率上昇を防ぎ、安定経営に役立つのです。
加えて、経営判断のスピード向上や将来への資金投資にも余裕が生まれます。
生産性の向上
人件費を変動費化することで、生産性の向上が期待できます。
固定給では成果に関係なく報酬が得られるため、形骸化した業務を漫然と続ける従業員が現れやすく、勤務時間をこなすだけのケースもあります。一方、売上に応じて人件費や人員が変動する仕組みは、従業員に成果への責任感を促し、業績向上への動機づけになります。
また、外注を活用すれば契約維持のため外注先は成果に強くコミットしやすく、結果的に企業全体の生産性が高まります。加えて業務を見直す機会にもなり、無駄な作業の削減にもつながるでしょう。
人件費のリスク回避
人件費を変動費化することで、経済ショックが起きても社員を解雇せずに済む可能性があります。
コロナ禍では固定費削減のために希望退職や退職勧奨を実施した企業が多く、東京商工リサーチの調査では回答企業のうち599社が人員削減を行い、その61.5%が景気回復後に人手不足に陥りました。一方、外注活用などで平常時から変動費化していた企業は、景気回復後の人材確保が速く、業務の標準化により早期に成果を上げやすいのです。
こうした備えが緊急時の生存率を高め、経営の持続性を大きく左右します。加えて、将来の事業拡大にも柔軟に対応しやすくなるでしょう。
人件費を固定費ではなく変動費にするデメリット
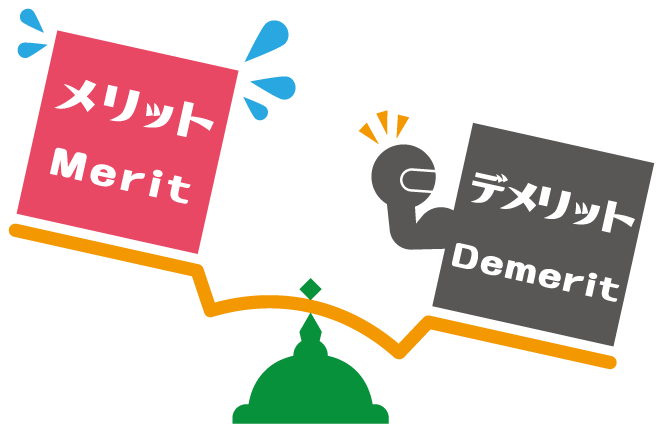
人件費を固定費ではなく変動費にすることで、経営の柔軟性やリスク回避につながる一方、注意すべきデメリットも存在します。外注や業務委託を増やすと、社内にノウハウが蓄積しにくくなったり、従業員の帰属意識が低下する恐れもあります。
ここでは、人件費を変動費化する際に直面しやすい課題やリスクについて詳しく解説します。導入前にぜひ確認しておきましょう。
人材管理工数の増加
人件費を変動費化するには、目標設定や成果の正確な評価が不可欠であり、人事部門の業務が複雑化し、負担が増加する可能性があります。
効果を上げるためには、社員ごとに適した達成可能なKPIを設定し、定量的指標だけでなくプロセス評価など定性的なKPIも取り入れることが重要です。優秀な社員の行動を基準にすれば行動変容を促せ、チーム貢献度を評価に加えればノウハウ共有が進みます。
こうした綿密な運用にはコスト増のリスクも伴いますが、それを上回る成果を狙えるでしょう。結果として組織全体の競争力向上にもつながるはずです。
社員のモチベーション低下
成果に応じて給与が変動する制度は、高すぎる目標を設定すると従業員のモチベーション低下を招きやすく、特に未達が続いた社員には過度なプレッシャーになります。
また、経理や研究開発のように成果を数値化しにくい職種では、何を目指せば評価されるのか不明確になりやすい点も課題です。さらに行き過ぎた成果主義は社員間に過剰な競争を生み、ノウハウ共有が進みにくくなるリスクもあります。
だからこそ緻密な目標設定と管理が不可欠で、その分コスト増も伴いますが、適切に運用できれば組織の健全な成長にもつながるでしょう。
採用率が低下する可能性も
優秀な人材を採用するには、安定した収入が欠かせません。
そのため、完全歩合制のように過度に変動費化された給与体系を導入すると、採用面で不利になることがあります。特にスキルの高い人材は子育て世代であることも多く、生活レベルを維持できないリスクを敬遠しがちです。
こうした層を惹きつけるには、安定した基本給を保証しつつ、成果が反映される報酬制度を組み合わせたハイブリッド型が有効です。例えば、成果を上げた社員にストックオプションを付与するなど、基本給に加えて変動費化を図れば、優秀な人材確保とモチベーション維持の両立が期待できます。
そもそも固定費と変動費の違いは?
そもそも固定費と変動費は何が違うのでしょうか。
簡単にいえば、固定費は売上や業績に関係なく一定額が発生する費用、変動費は売上や生産量に応じて増減する費用です。この違いを理解しておくことで、自社のコスト構造を正確に把握し、経営戦略や人件費の見直しを行う際の重要な判断材料になります。
利益改善を図るうえでも欠かせない基礎知識です。
固定費とは
固定費とは、売上や業績に関わらず毎月一定額が発生する費用のことです。
例えば、家賃やリース料、保険料、通信費、減価償却費などがこれにあたります。固定費の中でも大きな割合を占めるのが人件費で、一般的には固定費に分類されます。
ただし残業手当や繁忙期限定の派遣社員、アルバイト・パートの給与は売上に応じて増減するため変動費に含めることもあります。業種によっても固定費の内訳は異なり、製造業なら設備維持費、飲食店なら店舗家賃、小売業なら店舗運営費が中心です。
固定費を削減できれば、製造原価を下げ利益向上に直結するため、管理が非常に重要になります。
変動費とは
変動費とは、売上や生産量に比例して増減する費用のことです。
売上が増えると変動費も増え、逆に減少すれば変動費も減少します。代表的なものには、原材料費・仕入原価・販売手数料・消耗品費・支払手数料・荷造発送料・交際費・雑費などがあります。
例えば、500個の製品を製造するなら、その分の原材料が必要となり費用が増えます。このように売上に連動して動くため、変動費を正確に把握・管理することで、利益率や損益分岐点を見極めやすくなり、経営の安定化にもつながります。
まとめると、変動費は「売上に比例して変動し、原材料費や販売手数料、消耗品費などが該当」します。
固定費・変動費の分析指標
固定費と変動費の違いを理解したうえで、さらに経営を強化するには、それらを分析する指標を知ることが大切です。固定費や変動費が売上に対して適切なバランスかを把握することで、収益性の改善や資金繰りの安定化につながります。
ここでは代表的な分析指標を紹介し、その活用ポイントを具体的に解説していきますので、ぜひ参考にしてください。
限界利益
限界利益とは、売上高から変動費を差し引いて算出される、製品やサービスを販売して直接得られる利益のことです。つまり、製品やサービスが1単位売れるごとに企業が得る利益を示します。
<計算式>
限界利益=売上高-変動費
限界利益が高いほど損益分岐点が低くなり、少ない売上でも固定費を回収しやすくなるため、事業の収益性を評価する重要な指標です。
また、限界利益は「利益に固定費を加えたもの」とも表現でき、事業を継続するにはこの数値がプラスであることが最低条件です。
さらに、そこから固定費を引いた金額もプラスでなければ純粋な利益を確保できません。限界利益を正しく把握・分析することは、健全な経営判断や利益計画を立てるうえで欠かせません。
損益分岐点
損益分岐点とは、製品やサービスを提供する際に発生する費用と売上高がちょうど同じになるポイントのことを指します。
このときの売上高を「損益分岐点売上高」と呼び、企業が利益を出すにはこの水準を超える売上を確保する必要があります。損益分岐点は固定費と変動費のバランスによって決まり、固定費が多いほど、また変動費率が高いほど損益分岐点売上高は上昇します。
そのため、損益分岐点を下げるには固定費や変動費を削減する、逆に売上高を伸ばすために商品やサービスの単価を見直すなどの対策が有効です。損益分岐点を正確に把握することで、目標売上の設定や経営戦略の見直しが行いやすくなり、利益計画を立てる上でも大切な基準となります。
安全余裕率
安全余裕率とは、実際の売上高が損益分岐点売上高に対してどれほど余裕があるかを示す指標です。
<計算式>
安全余裕率=1-(損益分岐点売上高÷実際の売上高)
この数値は、売上がどの程度減少したら利益がゼロになるかを示しており、例えば安全余裕率が30%であれば、売上が30%減少すると損益分岐点に達してしまうことを意味します。安全余裕率がプラスで高いほど、財務的に余裕があり経営は安定しています。逆にマイナスの場合はすでに赤字を抱えている状態です。
一般的には40%以上が望ましいとされ、経営の健全性を示す重要な目安です。適切な安全余裕率を確保するためには、固定費や変動費の見直し、売上拡大策を講じるなどの対策が必要です。
売上高変動費比率
売上高変動費比率とは、売上高に対して変動費がどれだけの割合を占めているかを示す指標で、「変動比率」とも呼ばれます。
売上高は固定費・変動費・利益の3要素に分解され、この比率が高いほど変動費の占める割合が大きく、固定費が少ないため赤字リスクは比較的低く抑えられます。しかしその一方で、販売量が増えても変動費が大きいため、利益を増やしにくい構造とも言えます。
<計算式>
売上高変動費比率=変動費÷売上高×100
この比率は業種や企業規模によって異なりますが、中小企業庁のデータによれば平均はおおむね70〜80%程度とされています。売上高変動費比率を把握することで、自社のコスト構造を分析し、利益体質を改善するためのヒントが得られます。
人件費を固定費から変動費に変える3つの方法

ここまで人件費を変動費化するメリットやデメリットを見てきましたが、実際にはどのように進めればよいのでしょうか。人件費は企業経営において大きな固定費を占めるため、適切に変動費へシフトすることでリスクを抑え、より柔軟な経営が可能になります。
ここでは、人件費を固定費から変動費に変える具体的な3つの方法をご紹介します。
業績給を採用
人件費を業績と連動させる業績給を導入すれば、景気や業績が悪化した際に企業の固定費負担を軽減できます。
ただし、全国的に賃上げが進む中で基本給を引き下げるのは、従業員の不安や不満を招き、士気を大きく低下させる恐れがあります。そこで基本給はしっかり維持し、そのうえで変動部分の比率を高める方法が現実的です。
例えば、社員の努力や成果をポイント化し、それを商品交換や社員間での感謝の場に活用する企業も増えています。このようなインセンティブ制度は、人件費を変動費化しつつ、社員のやる気を引き出し、職場のコミュニケーション活性化にもつながるのが魅力です。
結果として、人件費を適正に保ちながら、組織の活力や生産性を向上させることが期待できます。
派遣社員や契約社員を採用
正社員を雇用する代わりに、パートタイムや契約社員、派遣社員を採用することで、労働時間や雇用期間を柔軟に調整できるのが大きな利点です。
これにより、人件費を固定費ではなく変動費として捉えやすくなり、売上や業務量に応じてコストを管理しやすくなります。さらに、非正規雇用の場合は複数人にシフトを割り当てることで業務負担を分散できるため、突発的な欠勤が出ても対応しやすいというメリットもあります。
一方で需要が落ち込んだ際には、勤務日数や時間を調整しやすく、人件費を抑制することが可能です。こうした採用形態を取り入れることで、固定費としての人件費負担を減らしつつ、必要なタイミングで必要な人員を確保できる、効率的で柔軟な組織運営が実現できます。
外注や業務委託を利用
業務の一部を外部の企業に委託するアウトソーシングを活用すれば、従業員を直接雇用する必要がなく、必要なタイミングで必要な分だけ人材を確保できるため、人件費を変動費化できます。
これにより、業務量の増減にも柔軟に対応でき、経営のリスクを抑えることが可能です。一方で、季節性や繁閑の差が大きい業務に正社員を配置すると、閑散期には仕事が減っても基本給という固定費は変わらず発生し、社員が時間を持て余すケースも出てきます。
こうした無駄を避けるためにも、業務の性質や繁忙期・閑散期の動きを踏まえ、適切にアウトソーシングを活用することが大切です。結果として固定費を抑えながら、必要な時には外部の力を借りることで効率よく人件費を管理し、利益確保や経営の安定化につなげられるでしょう。
人件費を削減したいなら、オンライン対応アシスタント『source』
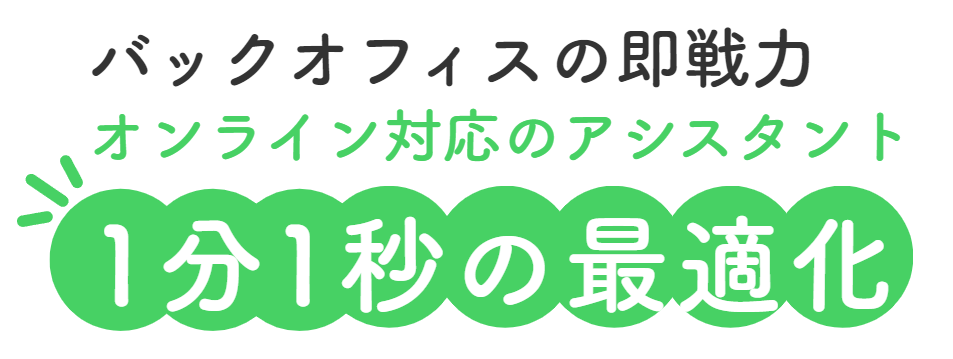
オンライン対応アシスタントの『source』を活用すれば、人件費を大幅に削減することが可能です。
通常、正社員やパートを雇用すると固定費として毎月一定の人件費が発生しますが、『source』なら必要な業務を必要なときだけ依頼できるため、完全に変動費として管理できます。さらに採用や教育にかかる手間やコストも不要で、専門スキルを持つスタッフにすぐに業務を任せられるのも大きな魅力です。
例えば、データ入力やリサーチ、メール対応といったバックオフィス業務を効率的にアウトソーシングできるので、社員はコア業務に専念可能。
結果として生産性が向上し、経営の効率化にもつながります。『source』は低コストで柔軟に活用でき、これからの時代の人件費対策に非常に適したサービスと言えるでしょう。
オンライン対応アシスタント『source』を無料で試してみる>>
まとめ
ここまで、人件費を固定費から変動費に変えるメリットや方法を整理してきました。
固定費を抑え、売上に応じて調整できる変動費化は、経営リスクの軽減や資金繰りの安定に有効です。まずは自社の人件費構造を分析し、アウトソーシングや業績給、非正規雇用の活用を検討しましょう。適切な仕組みを導入することで、利益率向上と組織の柔軟性を同時に実現できます。
加えて、社員のモチベーションを維持しつつ、持続可能な成長を目指しましょう。
おすすめの記事
-
ブログ
2023.11.14
【完全版】優秀な人なのに!辞める人が黙って辞めるのはなぜ?原因や…
-
ブログ
2023.11.14
辞めないと思っていた人が辞める理由と対策!兆候と放置リスクも解説
-
ブログ
2024.01.17
【切るべき?】派遣社員が使えない時の対処方法とは?社員の特徴も解…
-
ブログ
2024.01.17
人が辞めていく会社の末路とは?退職ラッシュで崩壊する職場
無料トライアル実施中!
まずはアシスタントとの連携のスムーズさを
実感してみてください!
ご新規の法人様へ、初回に限り3時間分の
無料トライアルをご用意しております。

単純業務を一旦お任せ
-
請求書の作成
-
営業リストの作成
-
Webサイトの更新
-
手紙の執筆代行
-
資料の作成・整理
ご新規の法人様へ、初回に限り3時間分の
無料トライアルをご用意しております。
3時間無料トライアルフォーム

3時間無料トライアルフォーム

