ブログ詳細
業務マニュアル作成を成功させるコツは?作成方法や手順もあわせて解説
公開日 : 2025.07.22
更新日 : 2025.07.22
「業務の属人化やミスが多い」そんな悩みはありませんか?
業務マニュアルを作成すれば、誰でも同じ品質で仕事を進められ、引き継ぎもスムーズです。
本記事では、マニュアル作成の4つの目的から、わかりやすいマニュアルを作る6つの手順、効果的な形式や作成方法、成功のコツまで詳しく解説します。
新人教育や効率化、チームのレベルアップを図りたい方にも役立つ内容なので、ぜひ最後までご覧ください。明日から取り組めるヒントが満載です。
なぜ業務マニュアルを作成するのか?4つの目的
なぜ業務マニュアルを作成する必要があるのでしょうか。
マニュアルは単なる手順書ではなく、業務の効率化や品質の安定、教育コストの削減、属人化を防ぐ重要なツールです。これにより誰が作業しても一定の成果が出せ、ミス防止にもつながります。
ここでは、業務マニュアルを作成する4つの目的を詳しく解説します。
業務の効率化
マニュアルを作成することは、業務効率化に直結します。
マニュアルがあれば、その都度やり方を思い出したり確認する手間が省け、作業スピードが向上し作業時間を短縮できます。また業務が可視化されることで、無駄な手順や工程に気づきやすくなるのも大きなメリットです。
実際に進めると、前例に従うだけの不要な作業や、重複作業、新人が同じミスを繰り返す例、部署間の作業時間の偏りなどが見えてきます。こうした問題を洗い出し改善につなげることで、生産性向上を図れるのです。
業務品質の安定
マニュアルを作成することで、業務の質を一定に保ち、常に安定した成果物を提供できるようになります。
マニュアルがない状態では、従業員それぞれのスキルや経験によって業務の進め方や成果物に差が出やすく、品質にばらつきが生じる恐れがあります。しかし、マニュアルを整備し、業務の手順やノウハウを従業員同士で共有することで、誰が担当しても同じレベルの作業を再現できるようになります。
その結果、サービスや製品の品質を一定に保つことができ、顧客対応や納品物のクオリティが安定し、信頼性の高い組織づくりにつながるのです。
教育コストの抑制
マニュアルには、具体的にどの作業をどの手順で進めるかが詳しく記載されています。
そのため、新入社員の研修や部署異動時の引き継ぎなどにも非常に役立ちます。教育が必要な人にあらかじめマニュアルを読んでもらえば、すべてを一から教える必要がなくなり、疑問点だけを指導者に確認する形で済みます。
これにより、教育にかかる時間や指導者の負担を大幅に減らすことが可能です。効率的な育成が進めば、その分ほかの業務にリソースを充てられるため、企業にとっては大きなメリットとなるでしょう。
属人化の防止
マニュアル作成には、業務の属人化を防ぐ重要な役割もあります。
属人化とは、特定の担当者しか業務を遂行できない状態のこと。これが続くと担当者の負担が増し、不在時には業務が遅延・停滞するリスクが高まります。さらに、休職や退職によりノウハウが引き継がれず、業務がブラックボックス化してしまう恐れもあります。
業務マニュアルがあれば、担当者がいなくても内容を確認しながら業務を進めることができ、誰でも一定の作業を遂行できる環境が整います。結果として、属人化を防ぎ、組織全体の安定的な運営が可能になるのです。
わかりやすい業務マニュアルに必要な6つの手順

業務マニュアルは、ただ作ればよいものではなく、誰が見ても理解しやすく実践できる内容であることが重要です。そのためには、作成における正しい手順を踏むことが欠かせません。
ここでは、わかりやすい業務マニュアルを作るために必要な6つの手順について、ポイントを押さえながらご紹介します。
1.業務マニュアルのターゲットを設定
まずは、業務マニュアルのターゲットを明確に決めることが大切です。
誰に向けて作るマニュアルなのかを最初に設定することで、どの程度の詳しさで、どのような言葉を使って説明すべきかが自然と見えてきます。
例えば、新入社員をターゲットにするなら、専門用語や業界特有の言い回しは極力避け、できるだけ平易な言葉を使って丁寧に説明する必要があります。また、図解や具体例を多く取り入れることで、理解度がぐっと上がるでしょう。
逆に、すでに経験を積んだ社員を対象にする場合は、基本的な説明は簡潔にし、ポイントを押さえた内容にすることで効率的に理解してもらえます。
このようにターゲットを意識して作成することは、わかりやすいマニュアルづくりの第一歩です。
2.何の業務のマニュアルを作成するのか決める
次に、マニュアルに盛り込む業務範囲をしっかり決めましょう。
これはマニュアル作成において非常に重要なステップです。範囲を曖昧にしたまま進めると、内容が広がりすぎて肝心な部分がぼやけてしまい、結果として使いづらいマニュアルになってしまう恐れがあります。
例えば「社内ブログの管理」をマニュアル化する場合でも、ブログ記事のライティングだけでなく、外部ライターの進行管理や校正、アクセス分析、既存記事の更新作業まで含めるかをあらかじめ明確にしておく必要があります。
どこまでをマニュアルの対象とするのかを整理しておくことで、作成にかかる時間を無駄にせず、利用者にとって必要十分な内容を備えた実用的なマニュアルを効率よく作ることができます。
3.業務マニュアルの内容と構成を設計する
次に、業務マニュアルの具体的な内容と構成を設計しましょう。
どの項目をどの順序で記載するかを決めることで、読み手にとって理解しやすいマニュアルになります。
例えば、まず業務の目的や全体フローを示し、そのあとで具体的な手順や注意点を順を追って説明する構成が一般的です。また、項目ごとに小見出しを付けたり、箇条書きを用いることで視覚的にも分かりやすくなります。さらに、FAQやトラブルシューティングのページを用意しておくと、万一のときにも自分で解決しやすくなります。
このように事前に構成を設計することで、情報が整理され、誰が読んでも迷わず実践できるマニュアルが作れるのです。
4.業務マニュアルを作成する
いよいよ実際にマニュアルを作成する段階です。
ExcelやWordを使って作成する方法も一般的ですが、最近では「マニュアル作成ツール」を活用する企業も増えています。これは誰でも簡単にマニュアルを作れる便利なツールで、あらかじめフォーマットやテンプレートが用意されているため、手順を入力するだけで統一感のあるマニュアルが作成可能です。
文章だけでなく、画像や図解を簡単に挿入できる機能もあり、視覚的にも分かりやすい内容に仕上げやすいのが魅力です。また、デザインや体裁が統一されるため、複数人で作成してもバラつきが出にくく、見やすく整理されたマニュアルを短時間で効率よく作れます。
5.実際に業務マニュアルを運用してみる
マニュアルが完成したら、いよいよ実際の業務で活用しましょう。
まずは従業員にマニュアルを使って業務を行ってもらい、運用上の問題点や分かりにくい箇所がないかを確認します。利用する中で気づいた改善点は随時反映し、より使いやすい内容にブラッシュアップすることが大切です。また、法律や規定の改正、業務フローの見直しなどにより、マニュアルの内容を変更しなければならないケースも出てきます。
古い情報のままではトラブルの原因となるため、定期的にマニュアルを見直し、最新の内容に更新することを習慣化しましょう。そうすることで、常に現場で役立つ実践的なマニュアルを維持できます。
6.実運用に合わせて業務マニュアルを修正
完成した業務マニュアルは作って終わりではなく、実際に現場で使って初めてその効果が試されます。
運用を始めてみると、想定していなかった作業の抜けや分かりにくい説明が見つかることも少なくありません。また、法律の改正や市場環境の変化、社内システムの入れ替えなどによって業務フロー自体が変わることもあります。
そのため、マニュアルは一度作ったら終わりではなく、現場の声や状況の変化に応じて随時見直し、修正を加えていくことが大切です。運用中に気づいた改善点は都度マニュアルに反映し、最新の状態を保つことで、常に実務に役立つマニュアルを維持できます。
こうしたサイクルを繰り返すことが、業務の質と効率を高め、組織の安定した運営につながるのです。
業務マニュアルのおすすめ形式
業務マニュアルを作成する際には、どの形式でまとめるかが大きなポイントです。
Excel・Wordのファイル、クラウド上で共有するオンラインマニュアルなど、さまざまな形式があります。それぞれにメリットや向いている使い方があるため、自社の業務内容や利用シーンに合ったものを選ぶことが大切です。
ここでは、業務マニュアルの代表的な形式とその特徴について分かりやすく解説します。
表が多いなら、Excel・Googleスプレッドシート
表や図を多く盛り込む業務マニュアルを作成するなら、Microsoft Excelを活用するのがおすすめです。
Excelは表計算ソフトであり、図やグラフを簡単に作成・編集できるだけでなく、それらをそのままマニュアル内に貼り付けられるため、視覚的に分かりやすい資料が作れます。また、タブ(シート)を複数設定すれば、一つのファイル内で関連データや複数の業務手順をまとめて管理できるので非常に便利です。
複雑な業務や数値管理が必要な場合にも特に適しています。
文章量が多いなら、word・Googleドキュメント
Microsoft WordやGoogleドキュメントは、クラウド上で利用できるWordサービスです。
共同編集が可能なため、複数人で同時にマニュアルを作成・改善できるのが大きなメリットです。インターネット環境があればどこからでもアクセスできる点も魅力です。
さらにWordは目次やページ番号が自動で追加され、印刷時もレイアウトが崩れにくいため、文章量が多いマニュアルを作成する際に特におすすめです。
デザインが重要なら、PowerPoint・Googleスライドショー
業務マニュアルに文字だけでなく、写真やグラフを多く入れたい場合は、Microsoft PowerPointの活用がおすすめです。
専門的な知識がなくても簡単に図解や装飾ができ、レイアウトも自由に調整できるため、デザイン性の高いマニュアルを作成できます。
視覚的に理解しやすくなるので、新人教育やプレゼン資料としても活用しやすく、多様な場面で役立ちます。見やすさや分かりやすさを重視する際に最適なツールです。
業務マニュアルの作成方法

業務マニュアルを効率よく作成するには、自社だけで抱え込まず、アウトソーシングの活用も有効です。加えて、専用のマニュアル作成ツールを使えば、誰でも統一感のある見やすいマニュアルを短時間で作成可能です。
ここでは、外部の力やツールをうまく取り入れながら、質の高いマニュアルを作る方法とポイントを具体的に紹介します。
アウトソーシングの活用
業務マニュアルを効率的に作成する方法の一つとして、アウトソーシングサービスを活用する手があります。
マニュアルの作成は大切な業務ですが、それ自体が直接利益を生む作業ではありません。そのため、自社の大切な人材がノンコア業務に時間を取られ、肝心のコア業務に注力できなくなっては意味がありません。マニュアル作成を外部に委託することで、従業員は本来取り組むべき業務に集中でき、生産性向上にもつながります。
さらに、専門知識を持つ業者に依頼すれば、第三者ならではの視点での改善提案や、豊富なノウハウ、他社の事例も学べるため、より実用的で質の高いマニュアルを作成できます。
マニュアル作成ツール
マニュアル作成ツールは、あらかじめフォーマットが整っているため、誰でも簡単に統一感のあるマニュアルを作れる便利なツールです。
文章だけでなく画像や動画の挿入もスムーズに行えるので、視覚的に理解しやすく、見やすいマニュアルを短時間で作成できます。さらに、ページ構成やデザインが自動で整うため、複数人で作ってもレイアウトにばらつきが出にくいのも魅力です。
ただし、こうしたツールには利用料がかかるケースが多く、導入にコストが発生する点はデメリットと言えます。しかし、作業効率や品質の高さを考慮すれば、十分に検討する価値のある選択肢です。
業務マニュアルを作る際のコツ
業務マニュアルは、ただ手順をまとめるだけでは十分とは言えません。
誰が見ても理解しやすく、実際に現場で役立つ内容にするためには、いくつかのポイントを押さえる必要があります。マニュアルの完成度が高ければ高いほど、業務の効率化やミス防止に大きな効果を発揮します。
ここでは、業務マニュアルを作る際に意識したいコツを具体的に解説しますので、ぜひ参考にしてください。
初心者でも分かりやすい内容を意識する
業務マニュアルを作る際のコツは、大きく3つあります。
まず1つ目は、伝えたいことをシンプルに書くこと。冗長な文章は読まれにくく、難解な言葉も理解を妨げます。簡潔で分かりやすい表現を使い、第三者にチェックしてもらうのも効果的です。
2つ目は初心者が読んで理解できる内容にすること。5W1Hを盛り込み、文章だけでなく画像や動画を使い補足することで理解度が上がります。
3つ目は読み手を具体的にイメージすること。新人や未経験者など、誰に読んでほしいのかを明確にし、その人に伝わる言葉を選ぶことがポイントです。
運用後も継続して改善し続ける
マニュアルは作って終わりではなく、運用後の継続的な見直しが欠かせません。
業務内容やOSなどの環境、組織体制の変化に応じて定期的にアップデートし、内容の古さや誤りを防ぎましょう。また、更新時に担当者が不在で困らないよう、あらかじめ役割や引き継ぎのルールを決めておくことも大切です。
さらに、見直しのタイミングを年に一度など定期的に設定しておけば、常に現場に合ったマニュアルを維持できます。こうした体制づくりがマニュアルの劣化を防ぎ、組織の安定運営につながるのです。
どんな方でも同じ作業ができる内容にする
マニュアルは抽象的な表現では行動に移しづらく、読み手が迷ってしまいます。
例えば「〇〇伝票を△△課に確認する」だけでは、伝票がない場合どうするかが分からず不十分です。具体的には「〇〇伝票の有無を当日15時までに△△課に確認し、あれば16時までに入力を完了させる」といったように、誰がいつまでに何をするのかを明確に示しましょう。
また「〇〇を△△するため」と目的やメリットを短く添えることで作業の意義が伝わりやすくなります。さらに時系列を示したタイムテーブルや図表を入れると、一連の流れが一目でわかり、実際に行動しやすいマニュアルになります。
マニュアルの作成なら、オンライン対応アシスタント『source』
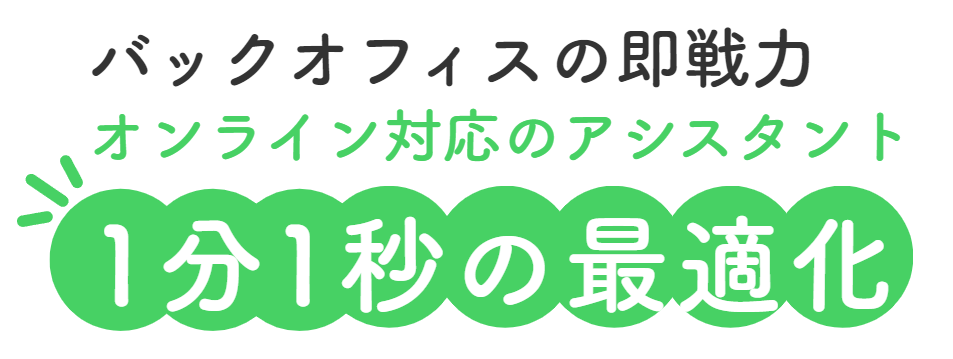
オンライン対応アシスタントサービス『source』を活用すれば、分かりやすい業務マニュアルの作成をプロに任せることができます。
マニュアル作成は重要ですが、社内の担当者が手探りで進めると時間も手間もかかりがちです。『source』なら専門知識を持つスタッフがヒアリングを通して業務内容を正確に把握し、誰にでも理解しやすいマニュアルに仕上げてくれます。
さらにオンライン対応なので場所を選ばず依頼でき、修正や追加の相談もスムーズ。フォーマットやデザインも統一されるため、見やすく整理されたマニュアルが短期間で完成します。自社の負担を大幅に減らしつつ、質の高いマニュアルを手に入れたい企業にとって、『source』は非常に心強い選択肢です。
オンライン対応アシスタント『source』を無料で試してみる>>
まとめ
ここまで、業務マニュアルを作成する目的や手順、ツール活用のポイント、アウトソーシングのメリットについて解説してきました。
マニュアルは業務の効率化や品質維持、教育コスト削減、属人化防止に役立つ重要なツールです。まずは自社の業務を洗い出し、優先してマニュアル化すべき業務を整理しましょう。自力で進めるのが難しければ、マニュアル作成に強い『source』のような外部サービスを活用するのもおすすめです。
早速小さな業務から着手し、社内のナレッジを蓄積していくことが、組織の成長につながります。
おすすめの記事
-
ブログ
2023.11.14
【完全版】優秀な人なのに!辞める人が黙って辞めるのはなぜ?原因や…
-
ブログ
2023.11.14
辞めないと思っていた人が辞める理由と対策!兆候と放置リスクも解説
-
ブログ
2024.01.17
【切るべき?】派遣社員が使えない時の対処方法とは?社員の特徴も解…
-
ブログ
2024.01.17
人が辞めていく会社の末路とは?退職ラッシュで崩壊する職場
無料トライアル実施中!
まずはアシスタントとの連携のスムーズさを
実感してみてください!
ご新規の法人様へ、初回に限り3時間分の
無料トライアルをご用意しております。

単純業務を一旦お任せ
-
請求書の作成
-
営業リストの作成
-
Webサイトの更新
-
手紙の執筆代行
-
資料の作成・整理
ご新規の法人様へ、初回に限り3時間分の
無料トライアルをご用意しております。
3時間無料トライアルフォーム

3時間無料トライアルフォーム

