ブログ詳細
失敗しない作業手順書の作成方法とステップを徹底解説!
公開日 : 2025.08.19
更新日 : 2025.08.19
「作業手順書」と「マニュアル」の違い、理解できていますか?
伝わらない手順書は、ミスや属人化の原因にもなりかねません。
本記事では、失敗しない作業手順書の作成手順やメリット、よくある失敗例とその対策、さらに作成のコツまで徹底解説します。効率的な業務運用に欠かせない手順書を、誰でも作れるようになります。
初心者にもわかりやすく、すぐに実践できる内容を厳選してお届けします。現場の悩みを解決したい方は、ぜひご一読ください。
作業手順書とマニュアルの違いは?
一言で言えば、手順書はマニュアルの一種です。マニュアルは業務全体の流れや背景、ノウハウなど広範囲な情報を網羅し、業務の効率化や成果を目的としています。
一方、手順書はその中でも特定の作業における手順や流れを具体的に記したものです。
たとえば、介護ヘルパー向けの調理業務マニュアルには、必要なスキル基準や注意点、なぜその手順が重要なのかといった情報が盛り込まれ、その中に「調理の下準備の手順書」が含まれるイメージです。
両者は混同されがちですが、マニュアルは全体像、手順書は個別の作業というように役割が明確に異なります。用途や目的に応じて使い分けることが重要です。正しく区別することで、より実践的で無駄のない業務設計が可能になります。
わかりやすい作業手順書の作成に必要な6つの手順

誰が読んでも迷わず作業できる手順書を作るには、ただ手順を書くだけでは不十分です。
現場で本当に役立つ手順書には、設計・運用・改善までを見据えた工夫が欠かせません。属人化やミスを防ぎ、業務効率を高めるためにも、ここではわかりやすく実用的な作業手順書を作成するための5つのステップを詳しく解説します。
1.作業手順書のターゲットを設定
まず、作業手順書の作成において重要なのは、利用者や利用目的、作業範囲を明確にすることです。
誰が、いつ、どんな目的で、どの業務を行う際に手順書を使うのかを事前に整理することで、掲載すべき情報が自然と絞り込まれ、無駄のない実用的な手順書が作成できます。その際に役立つのが「5W1H」の視点です。
- When(いつ)
- Where(どこで)
- Who(誰が)
- What(何を)
- Why(なぜ)
- How(どのように)
上記の要素を意識して構成することで、内容が具体的かつ明確になり、初めて読む人でも理解しやすくなります。
特に現場の新人や異動者など、業務に不慣れな人にとっては、背景や目的がわかるだけで理解度が大きく変わるため、最初の設計段階での整理が成功のカギとなります。
2.作業手順書の内容と構成を設計する
次に行うべきは、作業内容の洗い出しです。
まずは、業務の中でどんな作業が行われているのかを一つひとつ書き出し、全体像を整理しましょう。その際、単位作業(業務を構成する最小単位の作業)や注意点、所要時間、使用する道具なども併せてリスト化しておくと、より実用的な手順書になります。
また、判断が必要な場面については、迷わないように具体的な判断基準も明記しておくと安心です。作業を細かく可視化することで、意外と時間がかかっている工程や、作業順を入れ替えた方が効率的になるポイントなど、新たな気づきが得られることもあります。
こうした工程の見直しは、業務改善の第一歩にもつながります。結果的に、現場の負担軽減や教育コストの削減にも寄与するでしょう。
3.作業手順書を作成する
次に、洗い出した作業内容を構成と目次に沿って記述していきます。
ポイントは、常に利用者の立場に立って作成することです。専門用語を避け、誰が読んでも理解できるよう、具体的かつシンプルな言葉で説明しましょう。文章だけでなく、写真や図解などの視覚情報を活用することで、より伝わりやすい手順書になります。
また、本来はマニュアルに含まれる内容ではありますが、「なぜこの手順が必要なのか」といった理由も簡潔に添えることで、利用者の理解度と納得感が深まり、結果として作業の質や再現性の向上につながります。
さらに、フォントのサイズや余白、色使いなども読みやすさを左右する大切な要素です。丁寧な記述と工夫が、現場で本当に使える手順書をつくる鍵となります。
4.実際に作業手順書を運用してみる
作業手順書が完成したら、実際にその手順通りに作業を行い、運用してみることが大切です。
頭の中で完璧にできたと思っていても、実際の現場で使ってみると、抜け漏れや分かりにくい点、想定していなかったトラブルなどが見つかることはよくあります。特に「思っていたより時間がかかる」「この手順の前に準備が必要」といった気づきが得られる貴重な工程です。
また、自分で検証するだけでなく、実際に業務を担当する第三者にもチェックしてもらうことで、より実践的な改善点が浮かび上がります。利用者目線での運用テストを行うことで、手順書の完成度は大きく向上します。定期的な運用・見直しを通じて、常に現場にフィットした状態を保ちましょう。
これにより、作業品質と効率が安定し、属人化の防止にもつながります
5.作業手順書を改善
作業手順書を完成させたら、次は実際にその手順通りに作業を行い、内容を検証することが重要です。
頭の中では完璧だと思っていても、実際に手を動かしてみると、抜け漏れやわかりにくい点、手順の前後関係の見直しなど、修正すべき部分が見えてくることがあります。
また、自分だけで検証するのではなく、第三者にも確認してもらうことで、より客観的な視点から改善点を発見できます。特に実際に業務を行う人の意見は非常に貴重です。こうしたフィードバックをもとに、修正と改善を繰り返していくことで、現場で本当に使える、実践的で精度の高い手順書に仕上げることができます。
改善こそが手順書の完成度を高めるカギであり、継続的な見直しも品質維持に不可欠です。
作業手順書を作成する4つのメリット
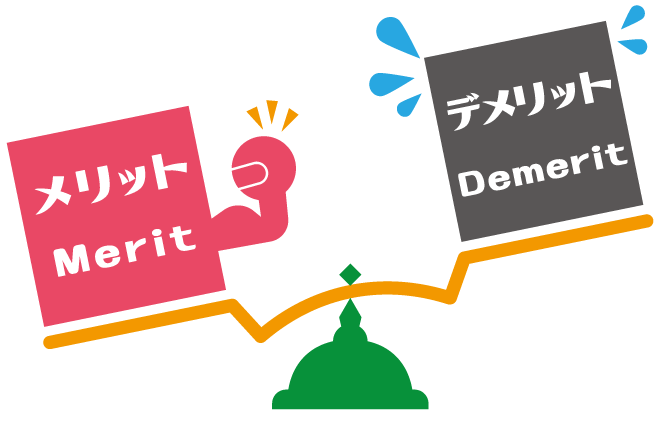
作業手順書は、業務を整理するためのツールであると同時に、現場力を高める強力な武器でもあります。
業務内容の「見える化」や品質の安定、さらには新人教育の効率化など、多くのメリットがあります。情報の属人化を防ぎ、組織の成長を支える基盤にもなります。
ここでは、作業手順書を作成することで得られる代表的な3つの効果をご紹介します。
1.業務内容を可視化できる
作業手順書を作成する大きなメリットのひとつが、業務の見える化です。
作業の流れが明確になっていないと、混乱やミスが起こりやすく、結果として効率が低下します。特に危険を伴う作業や、細かな注意が求められる業務においては、見える化による手順の明確化が欠かせません。
また、業務を標準化することで、新人からベテランまで誰もが同じクオリティで作業を行えるようになり、結果として組織全体の生産性や業務品質の向上にもつながります。
2.業務品質の標準化が可能
作業手順書のもうひとつの大きなメリットは、業務の標準化ができることです。
標準化によって、最短時間での作業完了、最高品質の成果、最適な手順による効率化、コストやリスクの最小化といった多くの利点が得られます。全員が同じ手順で作業することで、組織全体の業務の質とスピードが向上します。
さらに重要なのは、手順書を定期的に見直し、変化や新たな知見に応じて改善を加えること。こうした継続的な更新が、より実行しやすい業務環境を生み出します。
3.コツやノウハウの教育が容易になる
作業手順書には、作業者が培ってきたコツやノウハウを記録・共有できるという大きなメリットがあります。
長年の経験から得た貴重な知見も、個人の中だけにとどまっていては組織全体の成長にはつながりません。手順書にそれらを明文化することで、新人でも短期間でスキルを習得でき、誰もが最適な方法で業務を遂行できます。
また、担当者が変わっても同じ品質を維持できるようになり、企業にとって大きな財産となります。経験を共有し、組織力を高めましょう。
作業手順書の作成でよくある失敗例
作業手順書は、正しく作成・運用すれば業務効率を大きく向上させるツールですが、誤った作り方や運用では、かえって混乱や手間を招くこともあります。特に、要件定義の不足や運用後のメンテナンス放置、進捗管理の欠如はよくある失敗です。
ここでは、手順書作成時に陥りがちな代表的な失敗例とその対策を紹介します。失敗を避けるためのヒントとして、ぜひ参考にしてください。
作成前に要件定義ができていない
手順書に記載するスケジュールや要件定義が曖昧だと、読み手ごとの解釈にズレが生じ、納期の遅れや成果物の不一致といったトラブルにつながる恐れがあります。
こうしたリスクを防ぐには、手順書に5W1H(What:何を、Who:誰が、Where:どこで、Why:なぜ、When:いつ、How:どのように)を意識した具体的な情報を盛り込むことが重要です。特にスケジュールは、「月末まで」などの表現ではなく、明確な日付を記載することで誤解が生まれにくくなります。
読み手全員が同じ認識を持てる内容にしましょう。
運用後にメンテナンスしていない
作業手順書は、一度作成して共有すれば終わりというものではありません。
業務の内容や進め方は、時間の経過とともに少しずつ変化していきます。そのため、実際の運用状況に合わなくなった手順書を放置していると、現場で混乱を招いたり、ミスが発生したりする原因になります。
常に現場にフィットした内容を保つためには、定期的な見直しと更新が不可欠です。担当者や現場スタッフからのフィードバックを活かし、実態に即した形で手順書をメンテナンスし続けることが、信頼性の高い業務遂行につながります。
手順書の進捗管理ができていない
手順書にタスクが明確に可視化されていると、チーム全体で情報を共有しやすくなり、業務の効率化や生産性の向上につながります。
特に複数人で作業を分担する場合、各メンバーのタスク進捗を把握し、適切に連携を取ることが重要です。そのためには、手順書内に進捗管理用の記載欄を設けるのがおすすめです。日々の作業状況を確認できるようにし、チーム全体で進捗を共有する習慣をつけることで、作業の抜け漏れや遅延を防ぎ、よりスムーズな業務運営が可能になります。
定期的な進捗確認会議とあわせて運用すれば、さらなる成果も期待できるでしょう。
作業手順書を作成するコツ
作業手順書は、ただ業務の流れを文章で記載すればよいというものではありません。
実際に読む人が迷わず理解し、すぐに行動に移せる内容であることが大切です。そのためには、読みやすさや視認性、そして実用性を意識した工夫が欠かせません。
ここでは、誰が見ても分かりやすく、現場で使える手順書を作成するための3つのコツをご紹介します。
読み手が理解しやすい内容になるよう務める
手順書を作成する際は、実際に使う対象者を想定することが重要です。
読み手の立場によって、必要な情報のレベルや説明の深さが異なるためです。たとえば、対象が管理職であれば、社内ルールを理解している前提で簡潔にまとめることができます。
しかし、部署を問わず多くの人が利用する手順書の場合は、業務に不慣れな新入社員でも理解できるよう、丁寧な説明や用語解説を加えることが望ましいです。誰が読んでも迷わず作業できる、わかりやすい手順書を目指しましょう。
図やフローを加えると、さらに理解度が高まります。
表や図を積極的に使う
手順書を作成する際は、文字だけでなく積極的に表や図を活用しましょう。
視覚的な要素を取り入れることで、内容が格段に分かりやすくなり、作成の手間も軽減される場合があります。たとえば、クリックしてほしいボタンがある場合、文章で説明するよりも、ボタンを赤丸で囲み、番号を振って欄外に「クリック」と記載するだけで直感的に伝わります。
読者にとっても理解しやすく、迷わず操作できるのが大きな利点です。図や表は「多すぎるかも」と思うくらい挿入するのが、見やすく実用的な手順書をつくるコツです。
継続的に改善し続ける
作業手順書は、はじめから完璧を目指すのではなく、PDCAサイクルを意識して改善を重ねていくことが重要です。
PDCAとは、Plan(計画)・Do(実行)・Check(評価)・Action(改善)の4ステップを繰り返すフレームワークです。最初から完璧を求めすぎると、Planの段階で止まりがちになり、手順書の完成が遅れてしまいます。手順書は仮運用=Doを通じてこそ現場に即した実用的なものになります。
ある程度完成した段階で仮運用を試し、フィードバックを得ながらブラッシュアップしていきましょう。
作業手順書の作成なら、オンライン対応アシスタント『source』
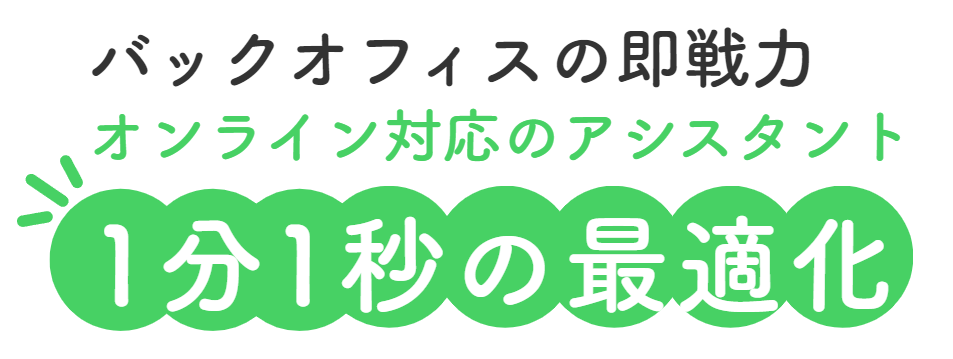
オンライン対応アシスタント『source』を活用すれば、誰でも分かりやすく実用的な作業手順書の作成をスムーズに進めることができます。
専門知識がなくても、プロのサポートを受けながら、構成や内容、見やすさまで考慮された手順書を効率的に作成可能です。表や図の活用、言葉選び、運用後の見直しポイントまで、現場で本当に使える手順書づくりをトータルで支援。オンラインで完結するため、全国どこからでも依頼ができ、スピーディかつ柔軟な対応も魅力です。
打ち合わせやフィードバックも丁寧に対応してくれるので、初めての方でも安心して任せられます。属人化を防ぎ、業務の標準化や教育の効率化を目指す企業に、『source』は心強いパートナーとなるでしょう。
オンライン対応アシスタント『source』を無料で試してみる>>
まとめ
作業手順書は、業務の可視化・標準化・ノウハウ継承を実現し、生産性向上に貢献する重要なツールです。
作成には、ターゲット設定から内容設計、記述、運用、改善まで一連の流れを意識することが大切です。視覚的な工夫や具体的な記載で、誰でも理解しやすい内容にしましょう。属人化を防ぐためにも継続的な見直しが不可欠です。
「手順書作成が難しい」と感じたら、オンラインアシスタント『source』に相談するのもおすすめです。
おすすめの記事
-
ブログ
2023.11.14
【完全版】優秀な人なのに!辞める人が黙って辞めるのはなぜ?原因や…
-
ブログ
2023.11.14
辞めないと思っていた人が辞める理由と対策!兆候と放置リスクも解説
-
ブログ
2024.01.17
【切るべき?】派遣社員が使えない時の対処方法とは?社員の特徴も解…
-
ブログ
2024.01.17
人が辞めていく会社の末路とは?退職ラッシュで崩壊する職場
無料トライアル実施中!
まずはアシスタントとの連携のスムーズさを
実感してみてください!
ご新規の法人様へ、初回に限り3時間分の
無料トライアルをご用意しております。

単純業務を一旦お任せ
-
請求書の作成
-
営業リストの作成
-
Webサイトの更新
-
手紙の執筆代行
-
資料の作成・整理
ご新規の法人様へ、初回に限り3時間分の
無料トライアルをご用意しております。
3時間無料トライアルフォーム

3時間無料トライアルフォーム

